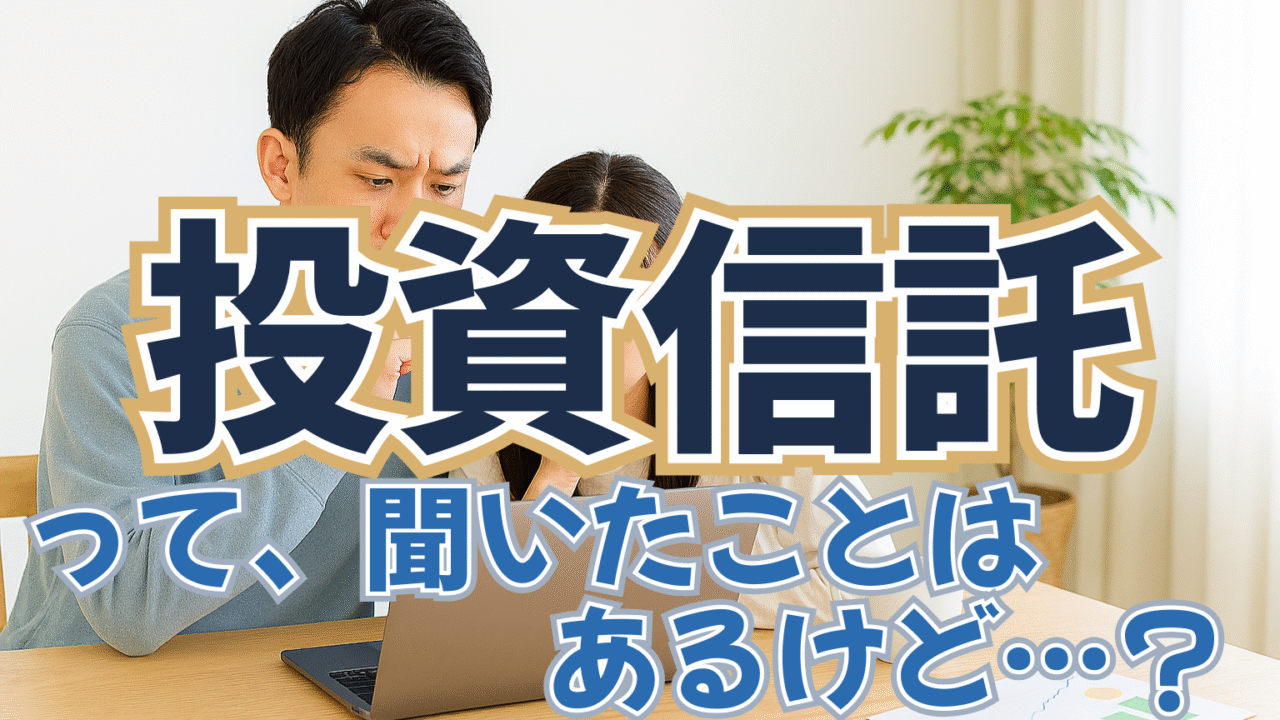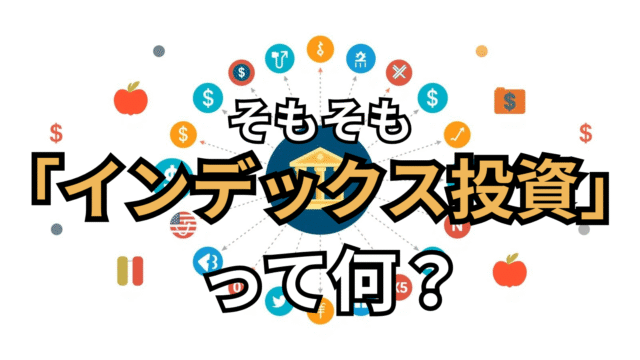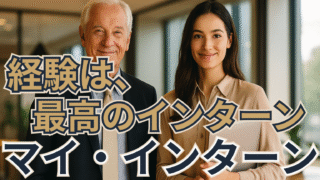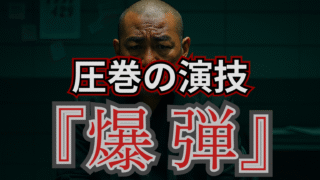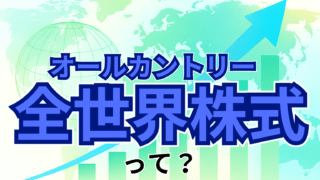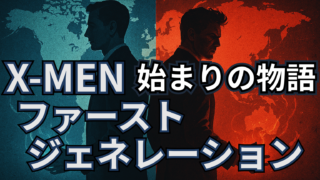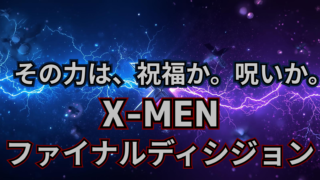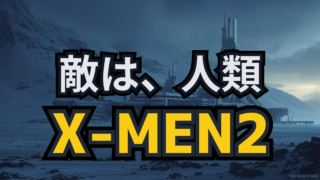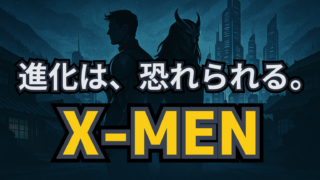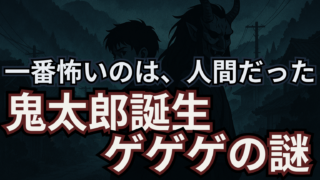※本画像はAIによるイメージ生成です。
投資信託という言葉は聞いたことがあっても、正直なところ最初の頃は自分も全く意味がわかりませんでした。
「お金を預けて運用してもらう…?でもどうやって利益が出るの?」と、頭の中は疑問だらけでした。
この記事では、そんな全く意味が分からなかった自分の経験を踏まえて、初心者の方でも理解しやすいように、投資信託の仕組みや選び方をかみくだいて説明します。
アクティブ型とインデックス型の違い、信託報酬の考え方、積立投資のコツ、そしておすすめの商品まで紹介するので、読み終わるころには「自分にもできそう」と感じてもらえる内容になっています。
🧑💼投資信託とは?
投資信託(とうししんたく)とは、たくさんの人から集めたお金を、投資のプロ(ファンドマネージャー)がまとめて運用してくれる商品です。
私たちは、その「プロが中身を考えてくれる投資商品(=おまかせパック)」を買うイメージです。
たとえるなら――
自分で材料をそろえて料理を作るのが「個別株投資」。
一方で、投資信託は「プロが栄養バランスを考えて作ったお弁当を買う」ようなものです。
中身(株・債券など)はおまかせでも、バランスよくいろいろな銘柄に投資できるのが魅力です。
個人ではなかなか手が出しにくい世界中の株や債券にも、少ない金額から分散して投資できるのが魅力。
「投資ってむずかしそう…」と思う人でも、手軽に始めやすい資産運用の方法です。
🔍 投資信託の2つのタイプ:「アクティブ型」と「インデックス型」
投資信託には大きく分けてアクティブ型とインデックス型の2種類があります。
■ アクティブ型
市場平均を上回る成果(リターン)を目指して、運用のプロが銘柄を選び、積極的に売買を行うタイプです。
魅力は「うまくいけば平均を上回る利益を狙える」点ですが、運用コストが高くなりやすいというデメリットがあります。
信託報酬が年1%前後になるものも多く、長期的にはコスト負担がパフォーマンスを圧迫することがあります。
■ インデックス型
一方、インデックス型は日経平均株価やS&P500などの「市場全体の平均値(インデックス)」に連動する運用を行います。
人が積極的に売買するわけではないため、手数料が低く、長期投資に向いているのが特徴です。
特に初心者には、このインデックス型を選ぶのが堅実です。
💰 信託報酬(手数料)を意識しよう
投資信託を選ぶ上で最も重要なのが**信託報酬(運用コスト)**です。
■信託報酬(しんたくほうしゅう)とは
投資信託を保有している間、運用会社に支払う手数料のことです。簡単に言うと、「プロにお金を運用してもらうための報酬」です。
▽ポイント
- 計算方法:運用している金額 × 信託報酬率
- 支払うタイミング:保有している間ずっと自動的に引かれる
- 表示方法:年率でパーセント表示(例:0.1%、0.5%など)
▽具体例
- 信託報酬 0.1%:100万円 × 0.1% = 年間1,000円
- 信託報酬 0.5%:100万円 × 0.5% = 年間5,000円
この差は一見わずかでも、10年・20年と長期になると大きな違いになります。
たとえば10年間では約4万円の差。運用益にも影響するため、信託報酬が安い商品を選ぶことが大切です。
🌍 低コストで人気のeMAXIS Slimシリーズ
信託報酬の低さで特に注目されているのが、三菱UFJアセットマネジメントの**「eMAXIS Slim」シリーズ**です。
このシリーズは「業界最低水準の運用コストをめざす」というコンセプトで知られ、代表的なものに以下の2つがあります。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
→ 世界中の株式に分散投資できる
→ 信託報酬:年0.05775%程度(2025年時点) - eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
→ 米国を代表する500社に連動
→ 信託報酬:年0.0814%程度(2025年時点)
どちらも信託報酬が0.1%以下と非常に安く、長期投資向きの優秀な商品です。
■なぜインデックス型は信託報酬が安い?
インデックス型は、日経平均やS&P500のような市場全体の指数に連動する運用を目指します。「市場平均に近い動きに合わせるだけ」なので、運用のプロが頻繁に銘柄を選んで売買する必要がありません。
一方、アクティブ型はプロが個別銘柄を分析して積極的に売買するため、人件費や調査コストがかかります。インデックス型は売買回数が少なく、運用の手間も少ないため、管理コストを低く抑えられます。
その結果、投資家が負担する信託報酬も非常に安く設定でき、長期で運用したときの手数料の差が運用益に大きく影響します。
この仕組みが、初心者でも安心して長期投資を行いやすい理由のひとつです。
💡 積立設定でドルコスト平均法を活用
投資信託のもうひとつの大きなメリットが、「自動積立ができる」ことです。
たとえば毎月1万円など、一定額をコツコツ積み立てることでドルコスト平均法を自然に実践できます。
これは、価格が高いときには少なく、安いときには多く購入することで平均取得単価を下げる効果がある投資法。
短期的な値動きに左右されにくく、長期的に安定した資産形成を目指せます。
📈 まとめ
投資信託は、プロに運用を任せながら少額から分散投資できる優れた仕組みです。
アクティブ型は高リターンを狙う積極派に向きますが、初心者には低コストで安定的なインデックス型が最適です。
特に「eMAXIS Slim」シリーズは、信託報酬が極めて安く、世界や米国市場の成長を手軽に取り込める点が魅力。
積立投資と組み合わせれば、無理なく長期で資産を育てることができます。
📎関連記事
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。